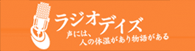二宮清純の視点
二宮清純が探る新たなるスポーツの地平線
2025.07.17
前編 誰もが簡単に安全に楽しめる
~フェンシングを通じた体験価値の提供~(前編)

スマートフェンシングは大日本印刷株式会社(DNP)に勤める天利哲也氏(コンテンツ・XRコミュニケーション本部)が、「フェンシング競技を誰でも簡単、安全に楽しむためのツール」として開発した。柔らかい剣やスマートフォンを用いてフェンシングの疑似体験ができる。天利氏は2024年にはスマートフェンシング普及のためスマートフェンシング協会を設立。今回は同協会代表の天利氏に加え、同協会の理事を務める東京五輪エペ男子団体金メダリスト・宇山賢氏からもスマートフェンシングについて話を訊いた。
 二宮清純: 天利さんが務めるDNPが開発したスマートフェンシングは昨年12月時点で述べ11万7000人もの方々が体験しています。このスマートフェンシングは日本発祥になるのでしょうか?
二宮清純: 天利さんが務めるDNPが開発したスマートフェンシングは昨年12月時点で述べ11万7000人もの方々が体験しています。このスマートフェンシングは日本発祥になるのでしょうか?
天利哲也: はい。私がつくりました。フェンシングを誰でも簡単に、安全にどこででも体験してもらうためのツールです。それが拡大し、いろいろなところでイベントを行っていますが、母体がフェンシングというものに変わりはありません。全くオリジナルのスポーツというわけではないんです。
二宮: 誰でも簡単にできるというのは、競技の入り口として大事な要素ですね。
天利: そうなんです。フェンシングをやろうと思っても金属の剣、防具やマスクと一式を揃えるだけでも一苦労。
伊藤数子(「挑戦者たち」編集長): 過去にその装具を揃えて体験会を開催。会社から「もう止めろ」と言われたとか?
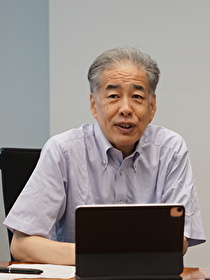 天利: 私自身、小学生から大学卒業までフェンシング選手でしたし、審判員も務めていました。本物を味わった方がいいのかなと思ったのですが、会社からは「金属の剣は危ないし、マスクや防具は夏場だと不衛生にもなる。二度とやるな」と言われました。そこで、簡単にフェンシング体験をできる方法がないかと模索し、最初はオモチャの剣を改造、電気審判機に接続する試作機をつくりました。それで2018年に体験会を行ってみたところ好評だったんです。
天利: 私自身、小学生から大学卒業までフェンシング選手でしたし、審判員も務めていました。本物を味わった方がいいのかなと思ったのですが、会社からは「金属の剣は危ないし、マスクや防具は夏場だと不衛生にもなる。二度とやるな」と言われました。そこで、簡単にフェンシング体験をできる方法がないかと模索し、最初はオモチャの剣を改造、電気審判機に接続する試作機をつくりました。それで2018年に体験会を行ってみたところ好評だったんです。
二宮: 体験会後の反響も大きかったと?
天利: はい。体験会の様子をSNSにアップすると、海外からも「これを貸してほしい」「体験会を開催してほしい」との要望をいただきました。2019年には東京オリンピック・パラリンピック1年前イベントでは、当時の国際オリンピック委員会(IOC)のトーマス・バッハ会長にも体験していただきました。
 伊藤: このスマートフェンシングが開発された頃は、宇山さんは現役選手でした。その時の印象は?
伊藤: このスマートフェンシングが開発された頃は、宇山さんは現役選手でした。その時の印象は?
宇山賢: 初めてスマートフェンシングに関わった時は、それこそ天利さんがほぼ手づくりのようなかたちで体験会を開催されていた時でした。その時はイベントのゲストとして、参加者の方たちと一緒にスマートフェンシングを体験するという立場だった。自分はフェンシングの審判機の配線をいじって設定する作業なども割と好きだったので自然とイベント運営を手伝うようになりました。
二宮: 現役引退後も関わっていくのが自然な流れだったと?
宇山: そうですね。2021年に現役を引退したタイミングで、自分が関わりたかったのは、強化よりも普及でした。スマートフェンシングは既に事業展開をされていましたし、どのようなプロジェクトかもわかっていた。今後も協力していきたいという気持ちで、今もその関係が続いているという感じですね。
【事業として収益化を実現】
 伊藤: スマートフェンシングはウレタン製の剣、導電性のあるジャケット、スマートフォン用のアプリを使って行います。
伊藤: スマートフェンシングはウレタン製の剣、導電性のあるジャケット、スマートフォン用のアプリを使って行います。
宇山: 導電性のジャケットは実際に競技で使用しているメタルジャケット(フルーレ、サーブル種目のみ使用)と同じ素材を使っています。
天利: 目を保護するためにゴーグルを着用しますが、ウレタン製の剣で身体を突かれてケガすることはほぼありません。フェンシングのスーツは本来ピチピチですが、スマートフェンシング用のジャケットは着脱しやすいようにベスト型になっています。これらを揃えれば、誰でも運営できるようなかたちになっています。
伊藤: どこでも、誰でもできるのが魅力ですね。
天利: そうですね。手間なく簡単にできるというのを重要視しています。試合時間やスコアを表示するためのスクリーンが必要になるので、屋内で行うのが基本になりますが、場所は選びませんね。
二宮: 今後はスマートフェンシングをきっかけにフェンシングを始める人が出てくるのでは?
天利: それこそがスマートフェンシングを開発した動機のひとつです。フェンシング普及の課題は、全国各地にクラブチームやフェンシング部が少ないので、競技を始めようにもその環境がない。今後はフェンシングに興味を持った方の受け皿を増やしていくことが必要になってくると考えています。
二宮: ちなみに日本でどのくらいのクラブ数があるんですか?
天利: 登録が約200チームです。
宇山: それゆえ練習場も少ないんです。日本フェンシング協会で公式に認められているクラブは現状104しかありません。加えて指導者が少ないというのが国内におけるフェンシングの実状です。
 伊藤: 今後についてはどのような展望を描いていますか?
伊藤: 今後についてはどのような展望を描いていますか?
天利: 静岡県沼津市、福島県川俣町との官民連携を強化しつつ、学校や教育機関、企業やスポーツ施設で体験会を行っていますが、事業としては収益化を実現できています。
二宮: それは素晴らしい。DNP内での事業としてスマートフェンシングを普及、推進しているんですね。
天利: もちろんです。私は構想段階からスマートフェンシングを持続可能なスポーツビジネスにするという思いでプロジェクトを進めてきました。収益化できる事業ならば、広く展開することもできるはず。フェンシング普及のみならず、スポーツ普及に繋がればと思っています。
(後編につづく)
<天利哲也(あまり・てつや)プロフィール>
スマートフェンシング協会代表。1995年、東京都出身。2007年、大日本印刷株式会社入社し、2016年からスポーツビジネスに携わる。小学生から大学卒業まで競技者としてフェンシングを続けてきたことから、手軽に運営でき、誰でも安全に体験ができるスマートフェンシングを開発。様々なイベントに「身近ではないスポーツの体験」という新しいコンテンツを提供。2024年にスマートフェンシング協会を設立。また大学在学中に国際審判ライセンスを取得し、仕事と並行してフェンシングや車いすフェンシングの国際審判員として活動している。東京オリンピック・パラリンピックでは、フェンシングとパラフェンシングの両競技の審判員を務めた。競技発展に向けても公益社団法人日本フェンシング協会、一般社団法人日本パラフェンシング協会と連動しスマートフェンシングを活用している。
<宇山賢(うやま・さとる)プロフィール>
スマートフェンシング協会理事。1991年、香川県出身。中学生の時に兄の影響でフェンシング競技を始める。大学3年時よりナショナルチームにて日本代表選手として活動。一度は競技を断念し大手家具メーカーに就職するも、オリンピックの開催地が東京に決定したことで競技の環境を整えることを決意。日本オリンピック委員会(JOC)が推進する企業とアスリートのマッチング制度「アスナビ」にて大手電機メーカーに入社し、競技中心ながらも宣伝部で体験型ショールームのPR業務を担当した。2021年に開催された東京オリンピックに日本代表として、男子エペ団体メンバー金メダル獲得に貢献。同年、現役選手を引退した。2022年に株式会社Es.relierを設立。フェンシングやスポーツの普及やキャリア等の課題解決に取り組んでいる。
(構成・杉浦泰介)