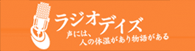二宮清純の視点
二宮清純が探る新たなるスポーツの地平線
2025.07.31
後編 社会課題解決にも有効
~フェンシングを通じた体験価値の提供~(後編)
伊藤数子(「挑戦者たち」編集長): 天利さんは昨年4月にスマートフェンシング協会を立ち上げました。創設の理由は?
天利哲也: 2019年にスマートフェンシングを創案し、大日本印刷株式会社(DNP)の事業としてスマートフェンシングの体験会を運営してきました。約5年が経過し、事業を拡大していく中、弊社だけでは手が回らなくなってきた。そこで社外の人に協力を仰ぎ、事業と活動をさらに広げていきたいと考え、協会を立ち上げました。社外の方の知見を集め、学校の授業やヘルスケア、フィットネスなど様々な用途へ展開していくことが狙いです。今後はスマートフェンシングのルールを策定し、公式大会の運営をしていくことも考えています。
 二宮清純: 宇山さんは協会理事に就任しました。
二宮清純: 宇山さんは協会理事に就任しました。
宇山賢: 引退後、体験会や学校での特別授業などで講師の依頼があり、その度にスマートフェンシングを活用していたことと、天利さんにアップデートの希望(演出、運営など)を伝えていたところ、元選手、また独自の視点からの知見を借りたいとお誘いいただきました。DNPという大手企業の事業に関わることができ、また協会の活動として公式に活動できることは、元アスリートのキャリアとしても有り難いことだなと感じました。
天利: 宇山さんは東京五輪エペ団体の金メダリストです。やはり体験会に彼が来ると、その価値は数十倍にはね上がる。参加する人たちの目の色が全然違うんです。
二宮: 金メダリストと"手合わせ"できるとなれば、参加者からも喜ばれるでしょうね。
宇山: 歓迎していただけるのは、ありがたいことです。私たちが大切にしているのは、体験する人たちに付加価値をどこまで届けられるか、です。例えば、スマートフェンシングを体験した際、その場で撮影した映像をリプレイで巻き戻し、親御さんや体験した本人が確認できるようにしています。そうすることで、自分の成功体験を可視化し、もう一段階、強く記憶に残してもらえるんです。
二宮: 成功体験がより深く刻み込まれるわけですね。
 天利: もちろん成功だけではありません。参加した皆さんは一様に、びっくりされるんですが、自分で思っている動きと、実際にリプレイで確認した動きがあまりにも違っているんです。
天利: もちろん成功だけではありません。参加した皆さんは一様に、びっくりされるんですが、自分で思っている動きと、実際にリプレイで確認した動きがあまりにも違っているんです。
二宮: 頭の中では、華麗な剣捌き、足捌きをしているつもりでも実際は違う、というケースが多いんでしょうね。
伊藤: 他にはどのような取り組みを?
天利: 体験会に4人家族など複数名でいらっしゃった場合、2対2のチーム戦を提案しています。これが非常に盛り上がるんです。また現役選手や元代表選手を体験会に呼ぶ時には、一般の方とのハンディキャップマッチを行います。従来のフェンシングに囚われない自由なかたちを提供することで、体験する人にもっと楽しんでもらえるのではないかと考えています。
【参加体験の増加を】
 二宮: スマートフェンシングは、フェンシング競技の入り口として生まれたものですが、これはパラフェンシングに置き換えることもできますね。
二宮: スマートフェンシングは、フェンシング競技の入り口として生まれたものですが、これはパラフェンシングに置き換えることもできますね。
天利: その通りです。パラフェンシングは車いすを固定した状態で行います、それは、かつて車いすフェンシングと呼ばれたものです。フェンシングと同じ剣や防具を使用し、ルールもフェンシングの競技規則に準じています。スマートフェンシングは、車いすに乗ったまま行うことができますし、固定したいすに座って対戦することも可能です。現在、私たちは、いすと車いすのどちらでも体験できるように進めています。他にも聴覚に障がいのある方、視覚に障がいのある方も参加できる体験会の開催も考えています。
二宮: 超高齢社会を迎え、健康寿命との格差が生じている今、ヘルスケアとしてのスポーツの役割は小さくありません。
宇山: 健康寿命の延伸のためには、下肢筋力を鍛えることが必要です。これは運動不足や筋力不足が指摘されている子どもたちにも言えること。下肢筋力を鍛えるための効果的な運動のひとつとしてスマートフェンシングをアピールできるのではないかと考えています。
二宮: フェンシングは全身運動ですが、基本は下半身が重要ということでしょうか?
宇山: そうですね。鋭いステップワークを生むのは強靭な足腰です。加えて攻防で大事なのは"間合い"をコントロールすること。剣は"間合い"を生み出すものでもあります。
天利: 距離感とタイミングが大事ですね。
二宮: 昔の子どもは、キャッチボールや虫捕りなど遊びから距離感が培われていきました。しかし、近年はゲームやスマートフォンの普及などによって、屋外で遊ぶ子どもが減っています。
宇山: フェンシングでは間合いの調整能力、空間認識能力と言われるものが必要になります。先に仕掛けるか、相手の仕掛けに合わせて技を返すのか。相手の間合いや狙いを感じ取ることは、生きていく上でも必要なことですよね。いわゆる"察しの文化"が失われつつある今、スマートフェンシングには、その想像力が養われる効果もあります。
二宮: さて協会としては今後、どのような活動を考えていますか?
天利: 多くの企業・自治体等との協業を進め、公式大会や全国大会の開催、全国の各地域でのキャラバン開催などを推進していきたいと思っています。また体育の授業など、教育現場においてスマートフェンシングの導入を目指します。
伊藤: 新たな用具の開発も?
 天利: そうですね。現在のスマートフェンシングはベスト型のメタルジャケットを着用していますが、これが不要になるタイプの剣を開発中です。新しい剣は静電容量の変化に反応するタッチセンサーの仕組みを応用しています。剣が人体に触れるとランプが点きますが、床を突いても反応はしない。ジャケットが不要になることで、よりスマートフェンシング体験が簡単にできます。体験会を運営しやすくなりますし、私たちの活動を、さらに広げられると考えています。
天利: そうですね。現在のスマートフェンシングはベスト型のメタルジャケットを着用していますが、これが不要になるタイプの剣を開発中です。新しい剣は静電容量の変化に反応するタッチセンサーの仕組みを応用しています。剣が人体に触れるとランプが点きますが、床を突いても反応はしない。ジャケットが不要になることで、よりスマートフェンシング体験が簡単にできます。体験会を運営しやすくなりますし、私たちの活動を、さらに広げられると考えています。
二宮: 宇山さんは?
宇山: 私はスマートフェンシングというツールに教育、スポーツ振興、ヘルスケア、福祉などメッセージを付与したパッケージを開発していきたいと考えています。また学術的なアプローチも大学などの教育機関と協力しながら進めてまいります。プレーヤーのみの視点ではなく、スポーツ基本法改正案にも明記されているスポーツを「する」「見る」「支える」「集まる」「繋がる」という役割を果たしつつ、フェンシングと多くの人々を繋ぐものとして価値を向上させていきたいと思っています。私が設立した株式会社Es.relier(エスリエール)という社名はフランス語でフェンシング(escrime)と人々を繋げる(relier)を合わせた造語。その点は弊社としても大切にしていきたいことと一致しているのです。

(おわり)
<天利哲也(あまり・てつや)プロフィール>
スマートフェンシング協会代表。1995年、東京都出身。2007年、大日本印刷株式会社入社し、2016年からスポーツビジネスに携わる。小学生から大学卒業まで競技者としてフェンシングを続けてきたことから、手軽に運営でき、誰でも安全に体験ができるスマートフェンシングを開発。様々なイベントに「身近ではないスポーツの体験」という新しいコンテンツを提供。2024年にスマートフェンシング協会を設立。また大学在学中に国際審判ライセンスを取得し、仕事と並行してフェンシングや車いすフェンシングの国際審判員として活動している。東京オリンピック・パラリンピックでは、フェンシングとパラフェンシングの両競技の審判員を務めた。競技発展に向けても公益社団法人日本フェンシング協会、一般社団法人日本パラフェンシング協会と連動しスマートフェンシングを活用している。
<宇山賢(うやま・さとる)プロフィール>
スマートフェンシング協会理事。1991年、香川県出身。中学生の時に兄の影響でフェンシング競技を始める。大学3年時よりナショナルチームにて日本代表選手として活動。一度は競技を断念し大手家具メーカーに就職するも、オリンピックの開催地が東京に決定したことで競技の環境を整えることを決意。日本オリンピック委員会(JOC)が推進する企業とアスリートのマッチング制度「アスナビ」にて大手電機メーカーに入社し、競技中心ながらも宣伝部で体験型ショールームのPR業務を担当した。2021年に開催された東京オリンピックに日本代表として、男子エペ団体メンバー金メダル獲得に貢献。同年、現役選手を引退した。2022年に株式会社Es.relierを設立。フェンシングやスポーツの普及やキャリア等の課題解決に取り組んでいる。
(構成・杉浦泰介)